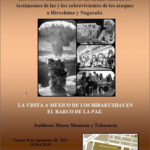ピースボートVoyage120はフランスのル・アーブル港に入港しました。ここは「印象派絵画の発祥の地」としても知られています。
そんなル・アーブルの隣の市「ゴンフレヴィル・ロルシェ市」は平和首長会議の繋がりで長年ピースボートと多くの平和活動をしてきました。今回もAlban・BURUNEAU(アルバン・ブルーノ)市長とICANフランスのJean-Marie Collin(ジャン-マリ・コリン)さんのオーガナイズのもと、中学生100名と市民50名へ向けて被爆証言活動をおこないました。

ICANフランスのJean-Marie Collin(ジャン-マリ・コリン)さん(写真左) とAlban・BURUNEAU(アルバン・ブルーノ)市長(写真右)
まず午前中は中学生に向けて被爆証言をします。
倉守さんは被爆当時は1歳。自身の記憶はありませんが、その後の生活で家族が放射能障害で苦しんでいたこと、自身は健康だったにもかかわらず被爆者として差別をされた経験を話します。
その後、4歳で被爆した伊藤さんは、亡くなった方をピラミッドのように重ねて火葬しているときの状況が今でも忘れることができずに嫌な思い出となっていることや、原子力発電所で事故が起こると原爆と同じように、またはそれ以上に放射能被害を与えるという危険性について話しました。
ほとんどの子どもたちが初めての戦争体験、そして被爆体験を聞きました。そのためその後の質問では
・倉守さんや伊藤さん以外の人は、その日はどうやって過ごしたのですか?
・家が無くなった人々はどうやって生活したのですか?
といったものもあり、原爆によって何が起こったのかわからない状況のなかで家族や親せきを探したり、病院に避難したり、壊れた家から使える木材などを利用してバラック小屋を建てて暮らしていたことを伝えました。
また、放射能の影響を気にして「広島や長崎に今も住んでいるのですか?危険ではないのですか?」という質問もありました。
「原爆での放射能は一瞬の出来事ですから、今は街も食物も安全です。だから安心して広島や長崎に遊びに来てください」と伊藤さんが笑顔で答えました。
午前中の証言会には、近隣の市の市長さんも聞きに来てくれ、会終了後には被爆者の二人に感想を伝えに来てくれました。

感想を伝えに来てくれた参加者
会終了後は、みんなで一度船に乗ってお昼休憩です。今回は、ブルーノ市長と近隣の市長3名を招いて船内でランチをしました。
ランチにはピースボート共同代表の川崎哲とICANフランスのジャン-マリ・コリンさんも同席し、ピースボートの活動や、ICANがイメージしている核兵器廃絶へのビジョンなどを共有しました。
平和首長会議に加盟しているゴンフレヴィル・ロルシェ市はもちろんこと、過去に開催された平和イベントなどを知っている近隣市長からの反応も好印象で、ジャン-マリ・コリンさんは「ICANシティアピールに新たな都市が加盟してくれそうだ」と手ごたえを感じていました。
みんなでランチ後、夕方からおこなう証言会の時間まで、市長の秘書であるステファンさんが車を出してル・アーブル市内観光に連れて行ってくれました。
最初に連れて行ってくれたのは港が見渡せる小高い丘。その丘からはパシフィックワールド号はもちろんのこと、ステファンさんが住んでいる街も見えます。そしてそこから見える海岸線沿いはノルマンディー上陸作戦の戦場となったところだそうです。説明パネルを見ながら、ステファンさんが、どの国がどの方角から攻めてきたのか、なぜドイツ軍のいたル・アーブル市ではなく海岸から攻めてきたのか歴史を教えてくれました。

港の見える丘で記念撮影
そして集中空爆によって破壊された街を再建するときに活躍したのが建築家の一人がオーギュスト・ペレ氏。オーギュスト氏は鉄筋コンクリートを使用し再建した建物は多くありますが、灯台のようにそびえたち街のシンボルとなっている「サン・ジョセフ教会」も訪れました。
この教会は戦争犠牲者への追悼も込められており、107mもある建物内は多くのステンドグラスによって幻想的な景色が広がっていました。

サン・ジョセフ教会の内部
市内観光を終えた後、午前訪れた会場へと再び戻ってきました。地元市民に向けての証言会をするためです。
40名ほどの方が集まり証言会が始まりました。午前中の話よりももう少し詳しく、放射能の影響は世代を越えて出てくることや、福島で起こった原発事故を目の当たりにしてようやく「原発の安全神話は無いんだ」と実感したことなどを話します。
その話を聞いたICANフランスのジャンマリさんは、マーシャル諸島やカザフスタン、米国国内など世界には核実験によるヒバクシャもいて、その多くが遺伝性の病気など影響を受けていることや、何世代にわたって影響があるのかを研究し続けている機関があることを補足説明しました。
また、軍事費に対する質問もありその回答は、会場にいた国会議員のLECOQ Jean-Paul(レコック・ジャンーポール)さんが具体的な数字とともに回答しました。また、フランスの国会では野党が自由発言できる時間が設けられているそうで、今回は「核軍備にかかる費用と核軍縮にかかる費用を対比しながら説明し、核兵器禁止条約への批准を求める」といった内容を発言するために準備していると教えてくれました。

被爆者へのお礼を贈呈してもらいました
「フランスは核保有国」というイメージがありますが、市民レベルでみると核兵器反対を訴えている市町があります。「核兵器は持たないほうが国益なんだ」と市民みんなが思えば国も核兵器を放棄していきます。その動きを作るために活動している市長をはじめ多くの人々と交流したことによって、市民レベルでの連帯の必要性を感じた一日でした。
(文:橋本舞)