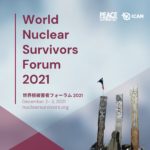2025年2月8日~9日の2日間、聖心女子大学のキャンパスを会場にしておこなわれた「核兵器をなくす国際市民フォーラム」
2日目は、メインホールだけでなくさまざまな教室で分科会が開催されました。
おりづるプロジェクトも1部屋をお借りし「Hibakusha Dialogue ー被爆者と出会い、語り合うカフェスペースー」を実施しました。
午前の回は、日本被団協 事務局次長の和田征子さんによる英語での証言会をおこない、登壇のために来日していた海外ゲストも視聴しに来ました。

証言を話す和田征子さん
「今も世界中で続く戦争についてどう思うか」と聞かれた和田さんは、
「武力になる前に対話をし続けることが大切。そして、戦争をさせないために国家補償の仕組みをはっきりさせる必要がある。(受忍論という)戦争で受けた被害を国民が負担するのはおかしな話。戦争中だけでなく終わったあとも補償が続くんだと国が理解すれば、戦争をしないことが一番効率がいいとなり戦争をしない考えになっていく」と、これからも国家補償を求める活動を続ける大切さを説きました。
午後の回では、千葉県八千代市原爆被爆者の会会長・中村紘さんと同会所属の小谷孝子さんお二人の証言会。
フォーラムに来ていた小・中学生くらいの子たちも聞きに来てくれ、会終了後には個別質問だけでなく、小谷さんによるプチ腹話術レッスンも開催されました。

個別で高校生からの質問に答える中村紘さん
お二人の話では原爆の威力や被害を身近なものにたとえて伝えており「教科書に出てくる昔の出来事」だったものが具体的に分かる内容でした。
そして「平和と平等は繋がっている。身近で起きるケンカや差別が大きくなると戦争になるんだよ。だからケンカじゃなくてお互いの違いを理解し受け入れることが大切なんだ」と話す中村さんの言葉は「子どもたちだけでなく、教育者にも聞いてほしい内容だ」との感想が寄せられました。

あっちゃんとあっちゃんママこと小谷孝子さん
日本被団協にもご協力いただき、会場には被爆証言をした3名以外にも被爆者の方にお越しいただき、興味のある方には個別で話ができる時間ももうけました。
被爆者と実際に話し触れ合い核問題が身近になることで、これから核廃絶への活動に関わる人が増えていくことでしょう。
文:橋本舞